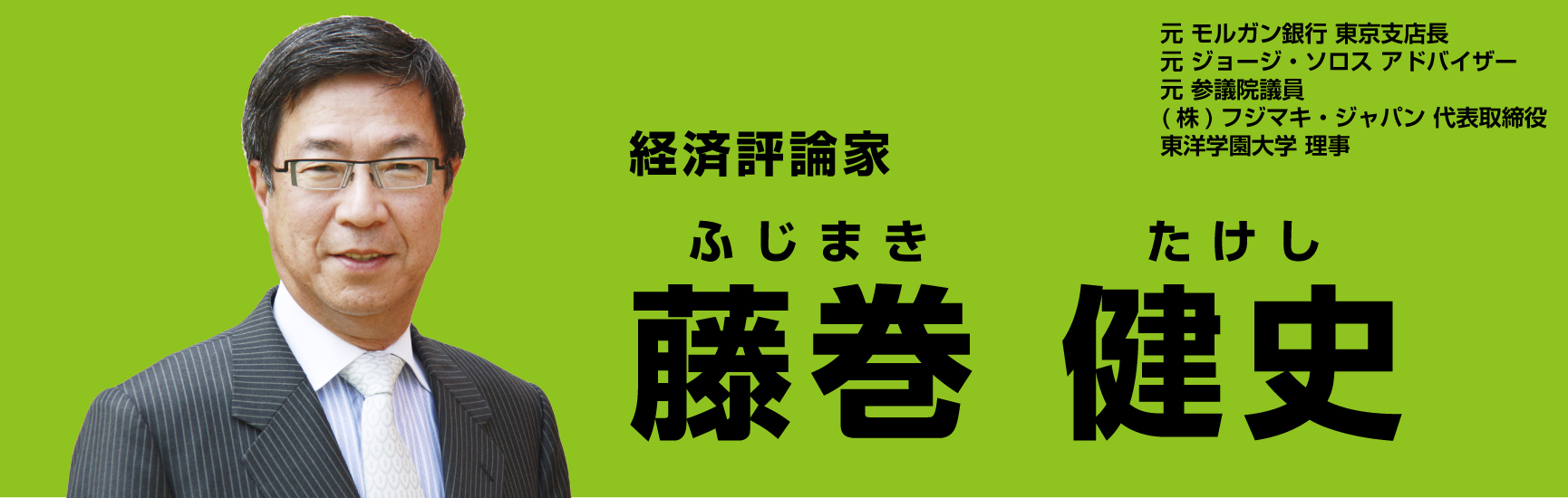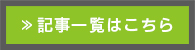1,「外国人の誤解を代表するような記述」
以下、ブルムバーグ時事。「マイナス金利政策が終了すれば、低迷する円相場は支えられ、余剰資金を日銀に預ける際に利子を支払わなければならない市中銀行の金融負担も軽減されるだろう。また、長期国債利回りの水準が切り上がり、日本の大手また、長期国債利回りの水準が切り上がり、日本の大手機関投資家が米国債などの資産を売却してより多くの資金を国内に振り向けるインセンティブを高めるだろう」
一番の誤解は、マイナス金利は約500兆円の日銀当座預金のうち、たったの30兆円の残高しかない。これが0.1%が0%に変わったところで、全銀行で1年間に300億円の利益しか増えないぞ。私が現役時代、一人で稼いでいた1年間のディーリング益より少ない。なにが、たったの300億円で「市中銀行の金融負担も軽減される」だ?
第2に「日本の大手機関投資家が米国債などの資産を売却してより多くの資金を国内に振り向ける」、。全否定はしないが、日本の銀行は米銀と違い為替リスクをほとんどとっていない。ドル短期調達/ドル長期運用だ。機関投資家も多くは為替ヘッジをしている。だから米日本人の米国債撤退は長期金利の上昇圧力にはなるが、為替には影響が少ない。資金の国家間の動きより米金利上昇の方が為替には影響する。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-08-09/RZ3G78T0G1KW01?srnd=cojp-v2
2、「ゴールドマンは、長期債に弱気なんではないの?」
ブルムバーグ記事。「今や米金融市場はある点で一致している。先週、10年債と30年債利回りを数年ぶりの高水準に押し上げた国債売りは、行き過ぎだったということだ」。その証拠は「ゴールドマン・サックス・グループとモルガン・スタンレーが30年物インフレ連動債の買いを顧客に呼び掛け」たからだそうだ。しかし呼びかけたのは、どうせアナリストだろう。しかもこのブルムバーグの記事の解釈は本当に正しいのか、私は、はなはだ疑問。
私は米国の物価連動債の取引をしたことはないので確とは言えないが私の理解だと物価連動債とは 表面利率は固定しているが 物価が上昇すれば元本が増え受け取れる利息が増額する仕組み。 すなわちインフレが加速すると魅力が増す商品。 ということは ゴールドマンとモルガンSのアナリストは長期固定金利債に関して弱気(金利上昇予想)なのではないの?ブルムバーグの解釈あっている?
8月1日の同じブルムバーグ記事には「ゴールドマン・サックス・グループは最大2本立ての社債発行を予定しており(略)10日に発表される米消費者物価指数(CPI)の前に、借り入れを手配したい意向のように見受けられる」この意味するところは明日のCPI の数字で長期金利のうわっぱねリスクを怖がっているということ。もしブルムバーグの解釈が正しいのなら(間違っているとは思うが)アナリストとリスクテーカーのマーケット読雄が異なっていることになる。
私は現役時代、アナリストの言葉には全く耳を傾けず、リスクを実際に取っている人(特にヘッジファンドのオーナーの意見)しか聞かなかったけどね。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-08-07/RZ1ELCDWRGG001